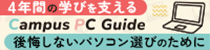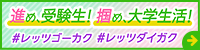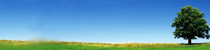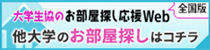掲載の情報は2024年度のものです。2025年度に向けてただ今準備中です。
教えて!学長!
~直撃インタビュー~
今回は2人の岩手大学生が小川智学長にお話を伺いました。

【インタビュアー】
岩手大学生協新入生サポートセンター 畠山彩香さん(教育学部 3年)
岩手大学生協学生委員会 佐藤優衣さん(農学部 4年)
(以下、敬称を略して表記します)
目次
1 海外体験について
2 大学と地域のつながり
3 パソコンについて
4 新入生へのメッセージ
多くのことを経験してほしい
佐藤:岩手大学のホームページに掲載されているWebパンフレットの「岩手で学び、世界で活躍する力を身につける」、「岩手から、世界中に発信していく」という内容を拝見し、グローバルな人材を求めていると感じています。
大学には、留学や研修などの様々な海外体験プログラムがありますよね。
少しご説明していただいてもよろしいでしょうか。
大学には、留学や研修などの様々な海外体験プログラムがありますよね。
少しご説明していただいてもよろしいでしょうか。
学長:岩手大学ではコロナ禍以前、毎年およそ200名の学生が海外へ渡航していましたが、落ち着きを見せた現在、再びより多くの学生に海外へ行ってもらいたいと思っています。
そのため、交換留学プログラムや奨学金制度、国際教育センターでの語学学習の支援や渡航手続きのサポートなどを積極的に行っています。また、学年暦では1年を4つのタームに区切って授業を行い、留学がしやすい環境も整えています。さらに、キャンパス内で留学生との交流体験ができるグローバルビレッジ等も用意しています。
人生のうちで海外経験ができる自由度が多くあるのは大学生の時なので、ぜひその期間を活用してもらいたいと思っています。大学から多くのサポートがあるので、学生にはアンテナを高くして、有効利用してもらいたいですね。新入生ではそのことをよく知らずに入ってくる人が多いので、入学後、効果的に情報を伝えていきたいと思っています。
そのため、交換留学プログラムや奨学金制度、国際教育センターでの語学学習の支援や渡航手続きのサポートなどを積極的に行っています。また、学年暦では1年を4つのタームに区切って授業を行い、留学がしやすい環境も整えています。さらに、キャンパス内で留学生との交流体験ができるグローバルビレッジ等も用意しています。
人生のうちで海外経験ができる自由度が多くあるのは大学生の時なので、ぜひその期間を活用してもらいたいと思っています。大学から多くのサポートがあるので、学生にはアンテナを高くして、有効利用してもらいたいですね。新入生ではそのことをよく知らずに入ってくる人が多いので、入学後、効果的に情報を伝えていきたいと思っています。
佐藤:なるほど。私は中学校の時に語学研修、高校ではオーストラリアに留学をしました。今度の新入生は、コロナの関係もあり、中学校や高校で留学するタイミングがなかった学生が多いと思います。
私は4年生なので実感していますが、大学1・2年生のうちに海外を経験することで将来の選択肢や視野が広がるなと思います。
学長が海外体験で得られることは具体的にどのようなことだと思いますか?
私は4年生なので実感していますが、大学1・2年生のうちに海外を経験することで将来の選択肢や視野が広がるなと思います。
学長が海外体験で得られることは具体的にどのようなことだと思いますか?
学長:歴史や文化の違い、我々が普通だと思っていることが実は普通ではないということ。自国をもっと知ることが、他国の人と付き合うのにどれだけ重要なのかということ。そして、自分の持つ人としての中身をどんどん膨らませてもらいたいと思っています。
言葉が上手じゃなくても思いは伝わるし、語学力を完璧に仕上げてから渡航する必要はありません。まずチャレンジして、様々な経験をすることがずっと大切です。
言葉が上手じゃなくても思いは伝わるし、語学力を完璧に仕上げてから渡航する必要はありません。まずチャレンジして、様々な経験をすることがずっと大切です。
佐藤:私も留学した時に「日本ってどんなところ?」と聞かれて「ここやここがよくて」と自分の言葉にできなかったという経験があります。自分の国はどういう国なのかとか、もっと難しい部分だと日本の政治についてなどを理解したうえで留学に行くと、より会話が楽しめるのかなと思いました。
学長:「今の総理大臣は誰?」という質問に答えられない人はいっぱいいますからね。
一同苦笑い
学長:日本の高校生や大学生は海外の学生と比べて座学での勉強を本当によくしています。では、その分海外の学生は何をしているかというと、色々なものを見て経験・体験しています。我々はテストで良い点が取れることを良しとする傾向にあると思いますが、学び方の違いを認識することが大切で、日本も少しずつ変わっていく必要があるかもしれませんね。
佐藤:4年生になったからこそ、海外体験に限らず、1・2年生のうちに色々な活動や経験をしてほしいなと感じていて、私は2020年度入学で1・2年生のうちに思い通りに活動できませんでした。本当はもっと海外に行ってみたり、ボランティアしてみたりとかもしたかったですが、できなかったという心残りがあります。学長先生が思う1・2年のうちにしておいた方が良いことや、おすすめすることがあれば教えていただきたいです。
学長:大学に来て、座学や実習で学んで、試験を受けて単位を取って、ということはもちろん大事だと思うのですが、私はもう一つ何かするという「プラス・ワン」が大切だと思っています。それはサークル活動でも、ボランティアなどの経験でも良いのですが、1年生のうちから何か1つまたは複数見つけて、講義等の学びにプラスして取り組んでほしいと思います。日本の高等教育はまだまだ受け身が多く、例えばグループディスカッションなどのトレーニングをする場というのが非常に限られているので、課外活動などで自然と身につけられると良いですね 。
佐藤:プラス・ワンでなにか経験してもらうことがこれからの新入生にとっては大切だということで。
学長:そう!君たちはもうプラス・ワン(学長へのインタビュー)やったからね!
一同笑う
佐藤:ぜひプラス・ワンを推していきたいです。ありがとうございました。

普段の学びにプラス・ワン の経験を
畠山:Webパンフレットで「地域の課題を体験し解決力を身に付ける」や「企業と共に地域社会の課題に取り組む」という文章を拝見しました。また、「岩手の大地と人とともに」をテーマにしていることから、岩手をとても大事にしていると感じています。具体的にどのように地域と関わり、何を学んでほしいと考えていますか?
学長:岩手大学は、国立大学の中でも最も地域との連携が深い大学として、高く評価されています。それは岩手大学という大学の大きさと、岩手県・盛岡市という行政区画の大きさがちょうどマッチしていて、関係者がコンタクトを取りやすいということが関係しています。さらに、一年を通して学長が知事や市長、地域企業の社長等と会う機会が多くあり、意見交換の場として有効です。地域に非常に密着している大学なので、学生達にも何か関わるチャンスを設けられるしくみが作れます。また、学内には地域の課題をテーマにした地域課題解決プログラムや、学生が地域の人達と一緒になって起業経験等ができる学内カンパニーという制度も用意しています。
学生:あーー(うなずく)
学長:大学の中で学生に教えるためのプログラムを作っていると、時には地域の抱えている課題が見えてこないこともあり、今年9月に「地域協創教育センター」というものを作りました。通常の大学内での学びにプラスして、自分の住んでいる地域の課題について学び、「じゃあ自分で起業して解決してみよう」などという意識を持つ学生を育てたいと思っています。学生が地域の人達と協力してローカルな視点で物事を見られるよう、今以上に地域の人達に大学教育へ協力してもらう企画です。
畠山:そうなんですね。私も盛岡に21年間住んで、地域について学ぶということはすごく大切なことだなと思っています。また、先ほど「地域協創教育センター」のお話がありましたが、具体的にどのような取り組みを行うか決まっていらっしゃいますか。
学長:「地域協創教育センター」で育てる人材というのは2つの大きな柱があって、一つはアントレプレナー人材、もう一つはソーシャルイノベーション人材です。アントレプレナーというのは、ビジネスを創出するために地域で事業を起こす人材を育てようということ。もう一つのソーシャルイノベーションというのは、地域の抱えている色々な問題を解決する人材を創ろうということ。この取組が文部科学省から認められて、今年の9月からセンターとしてスタートしたものです。
畠山:そうなんですね。
これから入ってくる学生にはぜひ先ほどのプラス・ワンを意識して行ってほしいなと思いました。ありがとうございます。
これから入ってくる学生にはぜひ先ほどのプラス・ワンを意識して行ってほしいなと思いました。ありがとうございます。
より高いレベルの情報教育を目指す
佐藤:パソコンについて伺います。岩手大学では、数年前にパソコンが必携化となったこともあり、「大学生がパソコンを持つこと」は当たり前になっています。
今後どのレベルまでパソコンを使えるようになってほしいなど岩手大学の学びについてどう考えていますか。
今後どのレベルまでパソコンを使えるようになってほしいなど岩手大学の学びについてどう考えていますか。
学長:今の社会に出てWord、Excelが全く使えないという状況は、ほぼあり得ないので、早いうちから学生に慣れてもらいたいと思います。これからの新入生は高等学校で情報の授業を受けてくるので、大学入学後は現在の情報基礎に加えて、もう少し高いレベルの教育が必要と考えています。大事なのは大学での情報教育によって、データサイエンスの知識をしっかり身に付けるということです。最低でも自在にパソコンが使えて、いろいろな表計算等がパソコン上でできるようになって卒業してほしいと思っています。
佐藤:先ほどもofficeのソフトを利用できると良いというお話がありましたが、学長のおっしゃる最低限のパソコンスキルは、Excelで関数を用いて計算したり、Wordで書式設定を使って文章を提出したりすることができるということでしょうか。
学長:授業での課題レポートの作成等に有効に利用してもらうことになります。最低でもWordとExcel、そして自分のやりたいことをプレゼンするためにはPowerPointが使えると良いですね。あと最近話題になっているChatGPTについては、学生や教職員が使う際の指針を出しています。私はいつも前向きに考えるほうで、時代とともに必要な物や事はどんどん取り入れていくべきだと思っています。ただどこまでやって良いかの判断は難しく、社会のルールに加え皆さんの心の中で線を引くことが大切です。情報リテラシーですね。
佐藤:ありがとうございます。
学長:自分の意思決定に必要なスキルを身に付けてもらいたいなと思っています。


大学入学はスタート
畠山:これから岩手大学に入ってくる新入生に、どんな気持ちで入学してきてほしいですか?
学長:岩手大学に入学した段階で、すでに自分の将来について一定の目標を持っている人、なんとなくこの分野が良いかなと思っている人、そして共通テストの結果を受けて(岩手大学に)決めた人、それぞれだと思います。でも、大事なのは入ってからであり、自分が大学を出る時にどうありたいのか、大学の4年間は考える時間が十分あるので、まずはスタートしましょう。大学に入学し、そこで何をするか、入った後の自分がどうあるべきかしっかりと考えることが大切です。あくまでも入学はスタートであり、色々な人と会い、様々な経験をし、多くのことを学んで、そして将来自分はどうしていきたいのか、ということを決めたうえで卒業してもらいたいと思っています。
畠山:ありがとうございます。私たちも3年、4年過ごしてきて、大学の4年間というのは、自分の将来の夢がある人もない人も、自分と向き合って自分を探していくような4年間だと思うので、私たちも新入生にそういう思いを伝えられるようにできたらいいなと思っています。
学長:コロナ禍の3年間で、学業にしてもサークル等の課外活動にしても、学生たちに大きな制約を強いてしまったとすごく感じています。その学生たちが社会に出た時、私たちはあの時に戻って、彼らに何をしてあげられたのか、もっとやれることがあったのではないかと思うことになります。しかしながら、通常では決してできない経験、この(コロナ禍の)経験があなた方お二人の人生にプラスに繋がるよう、コロナ禍の3年間を受け止めてもらえると嬉しいです。君たちの将来に期待していますね。
学生:笑う
畠山:ありがとうございます。
学長:これから君たち若者の時代ですよ。

【協力】
岩手大学学長 小川智
【取材・制作】
岩手大学生活協同組合
新入生サポートセンター広報局
岩手大学学長 小川智
【取材・制作】
岩手大学生活協同組合
新入生サポートセンター広報局
お問い合わせ